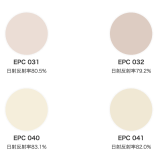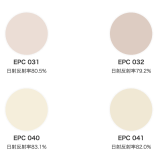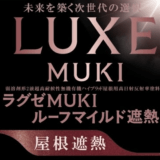2024.03.08
【プロが解説】「カチオン樹脂モルタル」ってどういう素材?セメントやコンクリートとの違いも解説!
カチオン樹脂モルタルとは?
「カチオン樹脂モルタル」とは、外壁塗装でよく用いられるモルタルの一種で、一般的には塗装の「下地補修」の際に使用されます。
そもそもモルタルというのは「マイナスの電気」を帯びているため、このカチオン樹脂と電子的に強く引き合います。もちろん従来のモルタルにも一定の強度はあるものの、付着力が弱く、クラック(ヒビ割れ)などが起こりやすいことからも、カチオン樹脂モルタルは非常に強い接着剤として重宝されているというわけです。
つまり従来のモルタルに比べて優れた接着力を持ち、ひび割れにも強い、というのがこのカチオン樹脂モルタルの特徴というわけです。
そもそも「カチオン」って何?
カチオンとは、プラスの電荷を持つ陽イオンのことです。このプラス電荷を持つカチオンは、マイナスの電荷を持つ陰イオンであるアニオンと強く引き付け合う特性を持っています。
つまり外壁塗装などに使われる「カチオンシーラー」や「カチオンフィラー」は、この電気的な接着力を利用しています。
多くの建築材料がマイナスの電荷を持っているため、これらカチオン性の材料を用いることで、より強固な接着が可能になり、安定した下地を形成できるのです。このようにカチオン特性を活用することで、耐久性の高くい仕上がりを実現できるのです。
下記記事では、塗料に使われる「カチオン」についてより詳しく解説していますので、こちらもあわせてご覧ください!
一般的な「セメントモルタル」と何が違うの?
①:一般的な「モルタル」について
モルタルとは、セメントに細骨材を加え、水で練り合わせた建築材料を指し、この一般的な形態を「セメントモルタル」と呼びます。
細骨材の種類は地域によって異なり、川砂や山砂などが使用されます。これによってモルタルの色や性質が変わり、細骨材の粗さが仕上がりに影響を与えるため、用途に応じて荒目・中目・細目の砂が選ばれます。特に、左官仕上げでは、さらに細かくしたふるい砂が使われることがあります。
モルタルには石灰や石膏を用いたバリエーションが存在しますが、ここでは主にセメントモルタルに焦点を当てています。
②:「樹脂モルタル」について
一方で樹脂モルタルとは、セメントの代わりに樹脂を主成分として使用しているモルタルを指します。
樹脂モルタルは一般的なモルタルと比べて、接着力や曲げ強度が高く、モルタルならではの中性化防止や防錆効果も期待できます。他にも乾燥が早いことや軽量であること、弾力性によるひび割れ防止などの利点があり、補修材料としての性能に優れています。
特に、エポキシ樹脂や合成樹脂エマルション(アクリルやエチレン塩ビなど)を含むタイプは、防水性や止水性に富んでいます。
これらの特性により、特に大きな損傷を受けた個所の補修に適しており、コンクリート補修に広く利用されているのです。
コンクリート・セメントとの違いは?
コンクリートとは
コンクリートは、細骨材の成分によって「セメントコンクリート」、「アスファルトコンクリート」、「レジンコンクリート」の大きく3つのタイプに分類されます。
まず「セメントコンクリート」は、セメントと水を混ぜ合わせたもので、一般的な建築物や構造物に用いられています。
次に「アスファルトコンクリート」は、アスファルト、つまり石油化合物を使用して細骨材を固めたもので、主に道路建設に活用されます。
最後の「レジンコンクリート」は、樹脂を用いて固めることで耐久性や耐化学性が要求される特殊な用途に適しています。
セメントについて
「セメント」とは、灰色の粉末で、水などを加えることで接着したり硬化したりする特性を持つ建築に欠かせない素材です。
特に、多用される「ポルトランドセメント」は石灰石や粘土を主原料とし、熱処理後に石膏を混ぜて製造されます。この名前は乾燥後の特性が「ポルトランドストーン」に似ていることに由来しています。
セメント自体は直接建材としては使用されず、水を加え加工することでコンクリートやモルタルとなり、建築材料としての役割を果たします。粉末状のセメントは保管性や運搬性に優れているため、工事現場で直前に加工されることが多いですが、大量に必要な場合はミキサー車でセメントを混ぜながら運搬されます。
外壁塗装を長持ちさせるには「適切な下地補修」が必須!
お化粧でも下地塗りが大切なように、外壁塗装もただ”塗料を塗るだけ”では、末長く美観を保てる良い塗装とは言えません。そのため下地材を使って下地補修を行うことが不可欠なのです。
本記事で紹介した「カチオン樹脂モルタル」というのは、分子レベルの強固な密着を実現するため、一般的な塗料よりも強力な下地材として機能します。
当社では職人歴【20年以上】の経験と知識をもとに、末長く美観を保てる外壁塗装を行います。
また外壁劣化の相談をすると「軽微なものでも塗装営業をされそう…」と思われるかもしれませんが、私たち馬渕塗工では、お客様のご自宅を丁寧に診断し、「やるべきならやる、やらなくてもよければ”経過見でOK”」としっかりお伝えしておりますので、ご安心ください。
放置し続けて手遅れになってしまわぬよう、ご自宅の外壁メンテナンス(塗装・塗り替え)ならお気軽にご相談ください!

2024.03.08
外壁塗装の「カチオンフィラー」って何のこと?塗装に適した箇所まで解説!
カチオンフィラーとは?
外壁塗装において、下地の小さな凹凸やひび割れを修正し、滑らかな表面を作り出すための下地調整材を「フィラー」と呼び、特にカチオン性樹脂を加えたものを「カチオンフィラー」といいます。
詳しくは後述しますが、フィラーは上塗りの寿命向上に加え、見た目も美しく仕上がる、下地の品質向上に欠かせない役割を果たしています。
また粘度が高く厚みを持つフィラーは、ダメージを受けた下地をシーラーよりも効果的に平滑にすることが可能です。
他にもシーラーとフィラーの機能を兼ね備え、小規模なひび割れもカバーする能力を持つ「微弾性フィラー」などの種類があります。
カチオンフィラーの「カチオン」って何?
カチオンとは、プラスの電荷を持つ陽イオンのことです。このプラス電荷を持つカチオンは、マイナスの電荷を持つ陰イオンであるアニオンと強く引き付け合う特性を持っています。
つまり外壁塗装などに使われる「カチオンシーラー」や「カチオンフィラー」は、この電気的な接着力を利用しています。
多くの建築材料がマイナスの電荷を持っているため、これらカチオン性の材料を用いることで、より強固な接着が可能になり、安定した下地を形成できるのです。このようにカチオン特性を活用することで、耐久性の高くい仕上がりを実現できるのです。
下記記事では、塗料に使われる「カチオン」についてより詳しく解説していますので、こちらもあわせてご覧ください!
フィラー・シーラーの違いは?
外壁塗装において、フィラーとシーラーは異なる役割を果たしています
「シーラー」というのは、塗料の密着を強化しつつ吸い込みムラを防ぎ、下地を補強する「下塗り材」として使用され、塗膜の性能を最大限に引き出す効果があります。
一方「フィラー」というのは、下地の凹凸を滑らかにする「下地調整材」として使用され、目止め作用があり、顔料や骨材、セメントといった無機成分が含まれているため、高粘度な性質があります。
どちらも塗装工程で重要な役割を持ち、外壁の仕上がりに大きく寄与しているのです。
カチオンフィラーは「劣化コンクリート・モルタル外壁」に効果的!
カチオンフィラーは、コンクリートやモルタル製の床に適用される材料です。
主に下地が劣化したり、不均一になった箇所の補修や調整を目的に用いられ、塗料の密着性を向上させる効果があります。
この工程は、上から施される防水工事等の下地処理に相当し、化粧下地が肌を整えるように、表面を平滑に整える役割を果たしているのです。
【注意】アスファルトやアルミニウムには使用不可!
カチオンフィラーは外壁塗装において素材との相性があり、使用に適さない素材も存在します。
具体的にはFRP、アスファルト、ポリエステル、アルミニウム、ステンレス、亜鉛メッキされた表面、油分を含む表面、フッ素やシリコン樹脂系の仕上げ材、撥水材やワックスが塗布された面、軟質の素材等が該当します。
つまり外壁塗装というのは、業者による適切な下地処理、他の製品の選定が重要になるというわけです。
適切な下地補修で、末長く美しい外壁塗装を!
お化粧でも下地塗りが大切なように、外壁塗装もただ”塗料を塗るだけ”では、末長く美観を保てる良い塗装とは言えません。そのため下地材を使って下地補修を行うことが不可欠なのです。
本記事で紹介した「カチオンフィラー」というのは、分子レベルの強固な密着を実現するため、一般的な塗料よりも強力な下地材として機能します。
当社では職人歴【20年以上】の経験と知識をもとに、外壁の素材・劣化状況にあわせた塗料選定で、末長く美観を保てる外壁塗装を行います。
また外壁劣化の相談をすると「軽微なものでも塗装営業をされそう…」と思われるかもしれませんが、私たち馬渕塗工では、お客様のご自宅を丁寧に診断し、「やるべきならやる、やらなくてもよければ”経過見でOK”」としっかりお伝えしておりますので、ご安心ください。
放置し続けて手遅れになってしまわぬよう、ご自宅の外壁メンテナンス(塗装・塗り替え)ならお気軽にご相談ください!
>>無料お見積り・ご相談はこちらから!
2024.03.10
スーパーセランフレックスにて上塗りを施工していきます
塗装工事における中塗りと上塗りの色選びについてご紹介します。
一般的に、中塗りと上塗りは同じ色を使用します。しかし、中塗りと上塗りで異なる色を用いることで、塗り残しがないか容易に確認できるという方法もあります。ただし、時間が経過し塗装が劣化すると、異なる色を用いた場合、中塗りと上塗りの色の差がはっきりと現れることがあります。
弊社では、このような長期的な劣化による見た目の問題を避けるため、通常は中塗りと上塗りに同じ色を推奨していますもちろん、お客様が色を変更されたい場合にはその要望に応じますが、これまでに弊社の説明を聞いた後に色を変更されたお客様はいません。
上塗り時の塗り残しに関しては、乾燥前は色が異なるため、発生する可能性は非常に低いです。このように、塗装の品質を保つための工夫と、お客様の期待に応える柔軟性を併せ持つことが、弊社の特徴です。
2024.03.10
スーパーセランフレックスにて中塗りを施工しています
サイディング板にリシン吹き付け仕上げの既存壁を塗装する際の工夫と注意点についてご紹介します。
まず、リシン材の粗いテクスチャーを均一に覆い、その「頭」が透けて見えないようにするため、塗装時には丁寧に何度も塗り重ねる必要があります。これは、見た目の美しさと質感を保つために重要です。
特に、板と板の間の「サネ」と呼ばれる部分は、まず刷毛で塗装し、その後すぐにローラーで仕上げることで、均一な仕上がりを実現します。この二段階の工程は、サネの部分だけが光らないようにするために必要です。全体的に塗装工事を行う際には、このような細部にまで注意を払いながら進めることが、仕上がりの質を高める上で非常に重要になります。
2024.03.04
下塗り・セラトーシツプラスにて施工しております
透湿性のある無機透湿微弾性フィラー「ダイヤセラ・トーシツプラス」という下塗り塗料を使用していきます。
ダイヤセラ・トーシツプラスは水性の為、臭いも少なく周囲にも環境にも職人にもやさしいです。
雨ばかりで施工出来ない日々が続いておりましたが、本日午後から何とか回復したため限られた時間ですが施工してきました。
下塗りが上塗り材の密着する部分になるため下塗りの段階で塗り残しが無い用に気を付けながら施工していきます。
2024.02.23
オートンイクシードを使用してシーリング施工をしました
プライマー施工後シーリングを目地底から充填し空気が入らないように打設して均して完成致しました。
窓枠などのシーリング打設後に直角になっていると窓枠が真四角な事もあり、かっこよく見えます。
2024.02.29
オートンイクシードを使用してシーリング工事を施工しておりました
オートンイクシードを使用し、数日間かけてシーリング工事を行いました。
まず、シーリング工事には「オートンイクシード」という特別な材料を使用しました。これは、耐久性と耐候性を大幅に向上させる特殊なポリマー、「LSポリマー」を含む先進のシーリング材です。この材料を使うことで、建物の外壁が長期間にわたり保護され、天候や時間の経過による損傷から守られます。
外壁は「リシン」という特殊な表面加工が施されているため、通常のマスキングテープがうまく貼り付かないという課題がありました。リシンは、モルタル外壁に細かい砂や石を混ぜた材料を吹き付けて作られ、表面をざらつかせる仕上げ材です。このざらついた表面は見た目にも独特で、比較的安価に新築住宅の外観を美しく仕上げるためによく使用されます。
この課題に対処するため、「風神ローラー」という特殊なローラーを用いました。
このローラーを使って、マスキングテープを外壁にしっかりと密着させ、作業のたびに丁寧に圧着していきました。これにより、塗装作業中の精度が大幅に向上し、外壁への塗装が均一に施されました。
最終的に、シーリング材を均一に打設し、整えることで作業は完成しました。
「シーリング工事の重要性」については、下記記事でも詳しく解説しています。
関連記事:『【プロが解説!】シーリング工事って何?気密・防水性を高める外壁工事を解説!』
2024.02.29
三種ケレンとアレスダイナミックプライマーで鉄部に下塗りをしました
まず「三種ケレン」というプロセスを用いて鉄部を下準備します。三種ケレンは、鉄部表面の錆や旧塗膜を適度に除去し、鋼面を露出させる作業です。この方法は、特に保護膜として機能している旧塗膜(活膜)を残す点で特徴があります。この活膜は、新しい塗料の付着を助ける重要な役割を担います。
下準備の後、鉄部に「アレスダイナミックプライマー」という下塗り材を塗布します。このプライマーは、亜鉛めっきやガルバリウム鋼板、アルミ、ステンレスなど、通常塗料が付着しにくい素材にも優れた付着性を示す最高級の防錆プライマーです。この塗料の使用により、鉄部は長期間にわたり錆や劣化から保護されます。
特に、庇(ひさし)や唐草(屋根の水切り部分)などの細部にも、この下塗りを丁寧に施工します。これらの部位は、水の侵入や集積により錆びやすいため、特に注意を払って処理されます。
鉄部塗装のこの段階での下塗りは非常に重要です。水性系の外壁塗料が鉄部に付着しても、適切な下塗りがされていないと塗料は密着せず、結果として鉄部の保護が不十分となります。しかし、このアレスダイナミックプライマーを使用することで、その後の塗料がしっかりと密着し、鉄部の保護を確実に行うことができます。
この作業では、施工の順序も重要です。適切な順序で施工を行わなければ、望ましい結果を得ることはできません。したがって、鉄部の下塗りは、外壁塗装工事における重要なステップの一つであり、専門知識と正確な施工技術が求められます。